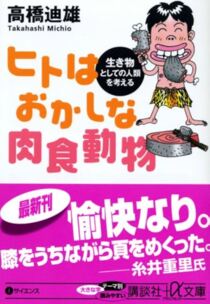
●ヒトの本性は肉食動物 (東京大学 農学生命科学研究科獣医生理学研究室教授 高橋 迪雄)
草食動物はバクテリアを発酵させるために、
消化管のどこかが目立った変化を見せます。
そのような観点でヒトの消化管を見ると、
ヒトの消化管はイヌやネコのそれと同様に際立った変形はなく、
肉食動物の特徴を備えています。
肉食動物は主としてたんぱく質を摂取し、そこからアミノ酸を得るとともに、
アミノ酸をエネルギー源としても使っています。
アミノ酸の末端に付いているアミノ基は、比較的容易に酵素の作用で外すことができます。
これが外されれば炭水化物になりますから、エネルギー源としても利用できるのです。
肉食動物の尿には多量の尿素が含まれていますが、これは、
アミノ酸がエネルギー源としても使われているためで、
アミノ酸から外されたアミノ基は肝臓で毒性の低い尿素に換えられ、
これが腎臓から排泄されています。
アミノ基が外された炭水化物は、最終的にはミトコンドリアで酸素によって酸化され、
ATPの形でエネルギーが取り出されます。
つまり、われわれの細胞にミトコンドリアが住み着いてくれているおかげで、
アミノ酸をエネルギー源として使うことは、きわめて容易なのです。
現代のヒトは、確かに植物性の食物をたくさん食べますが、
生理学的には肉食動物に違いありません。
したがって遊牧生活をしている人たちが、
最も自然に近い食生活をしていると言えるでしょう。
穀物を主たるエネルギー源にし始めたのは、人類400万年の歴史で、
農耕が始まったわずか1万年前のころのことだと考えられます。
さらに日本人は、この穀物についても、米と麦を併用するという
複雑な食生活を送っています。
「有機農業」をはじめとして、人間の食生活の自然回帰が叫ばれていますが、
文明人はもともと「自然」からは大変解離した様式で生活をしています。
寿命が著しく延長しているのも「自然」から大変解離した現象であることは確かで、
この延長した寿命、つまり50歳以後の寿命を健康に維持していくためには、
それなりの工夫をすることが必要かと思われます。
とくに、肉食動物が草食をしているのがわれわれですから、
高齢化に伴い食欲が落ち、さらに消化管機能が減退したときに、
どれだけのアミノ酸をどのように摂取するかは、
健康を維持していくための大問題になるかと思われます。
返信する